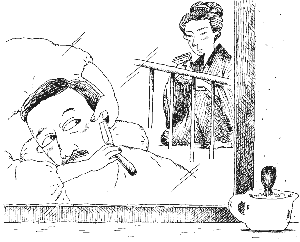 いま、秋になると「読書週間」という。昔は「灯火親しむ頃」といった。本を読む季節という。
いま、秋になると「読書週間」という。昔は「灯火親しむ頃」といった。本を読む季節という。
その昔に、夏目漱石は『夢十夜』という小品を書いた。明治四十一年ごろ「大阪朝日新聞」に、一回読み切りで連載した作品である。
その「八話」に理髪店の話がある。この夢話の理髪店は明治のころ、本郷帝大(現・東京大学)前の喜多床を書いたのだろうか、そっくりである。
喜多床客名簿には、漱石の名が載っていた。
……『床屋の敷居を跨いだら、白い着物を着て、かたまっていた三、四人が、一度に「いらっしゃい」と、いった。
真中に立って見廻すと、四角な部屋である。窓が二方に開いて、残る二方に鏡が懸っている。鏡の数を勘定したら六つあった。
自分は、その一つの前へきて腰をおろした。すると、お尻がぶくりと云った。余程、坐り心地が好く出来た椅子である。鏡には、自分の顔が立派に映った』(中略)
明治の理髪店は、敷居のある硝子戸の入口で、開け、閉めしたものである。洋館造りで、ドアはずっと後の話である。
当時、理髪師は和服が主で、その上に長い白衣を着ていた。コートに似たデザインの白衣である。
その頃、鏡が六つある店はハイクラスの理髪店だった。
二方にある鏡も、一方は大鏡(4×6)で店を飾ると同時に明るさを考えたものだろう。
いま一方は、ならんだ椅子五台の前の(3×4)の鏡か(2×3)の鏡だろう。大体、椅子の前の鏡は、(2×3)の鏡を使ったものである。
腰をおろすとぶくりとお尻のおちこむ椅子は、上等椅子で、スプリングがよくきいたものである。
……『顔の後には窓が見えた。それから帳場格子が斜に見えた。格子の中には人がいなかった。窓の外を通る往来の人の腰から上がよく見えた』
……『自分は薄い髭を捩って、どうだろう物になるだろうかと尋ねた。白い男は、何も云わずに手に持った琥珀色の櫛で軽く自分の頭を叩いた。
さあ、頭もだが、どうだろう物になるだろうか。と、自分は白い男に聞いた。
白い男は、矢張り何も答えずにちゃき、ちゃきと鋏を鳴らし始めた。
鏡に映る影を一つ残らず見るつもりで、眼をみはっていたが、鋏の鳴るたんびに黒い毛が飛んでくるので、恐ろしくなってやがて眼を閉ぢた』
……『やがて、白い男は、自分の横へ廻って、耳の所を刈り始めた。毛が前の方へ飛ばなくなったから、安心して眼を開けた。
栗餅やあ、餅やと云う声がすぐそこでする。小さい杵をわざと臼へあてて、拍子をとって餅を搗いている。
栗餅屋は、子供の時に見たばかりだから、一寸、様子が見たい。
けれども、栗餅屋は、決して鏡の中に出て来ない。只、餅を搗く音だけする。自分は、あるたけの視力で、鏡の角を覗きこむ様にして見た。
すると、帳場格子のうちに、いつの間にか一人の女が坐っている。
色の浅黒い、眉毛の濃い、大柄な女で、髪を銀杏返しに結って、黒繻子の半えりの掛った素袷で、立て膝のまま、札の勘定をしている』(後略)
参考資料:「夢十夜」(夏目漱石)
