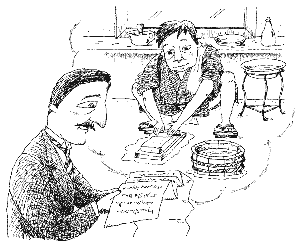 小泉八雲の小説に「乙吉の達磨」というのがある。
小泉八雲の小説に「乙吉の達磨」というのがある。
『乙吉さん-子供たちが達磨さんの左の眼をたたきつぶしたのですか』
へい、へいと云って乙吉は、上等の鰹を俎板(まないた)の上に取り上げながら、気の毒そうに笑いを含んで云った。
『はじめから左の眼はございません』
『こんな風に作ってあったのですか』と、私は、また訪ねた…。
八雲はこどもの頃、友達の過失で左眼を失い義眼だった。
この山口乙吉(焼津城之越)の家に滞在していた時にこんな話がある。明治三十四年の夏の話である。
『父は或る日、宿の近所の貧弱な理髪師にひげを剃らせました。薄紙で五、六度あごや頬を撫でられたと思うまに、もう綺麗に剃り上がっていたと、その技術に感服すると共に切れ味よき剃刀と、これを研ぐ砥石とに興味をおぼえ、早速、自分のナイフ(刃の四枚出る米国製品)を研がせによりました。このナイフは、前日父が私のために蒲鉾板を削って船を作ってくれた時、刃端を欠損したものでした。やがて、ナイフは美事に研ぎ上がってきました。
これで鉛筆や木片を切ってみて、そのすぐれた刃の味に父は再び感服しました。研ぎ料は三銭とのことでした。三銭とは余りに安い、五十銭やって呉れと父は奥村さんに申しました。それを二つ返事で畏り奉る程左様に父の命にたやすく従うよう母から仰せつかってきていぬ奥村会計主任は、その場で父に向かって反対はしませんでしたが、階下へ降りて乙吉さんに相談しました。
「物には相場があるのでのォ、十銭も過分だが先生様がせっかくそう云いなさるだで、じゃ二十銭もおやんなさるか」とのことに、奥村さんは我が意を得たりと二十銭やりました。
それでも「勿体にやァ」といって床屋はなかなか受けとらなかったそうです。それを、無理に掴まして帰った奥村さんはかくと自慢げに復命しますと、父は「すぐれた技術は容易に得難いものだ。それに対しては充分の敬意を払うべきである。私は、外観や名目に対して払うのではない」と意見を述べ、残りの三十銭を、君の巧妙なる技倆に報ゆる、とて床屋に贈りました。
父の帰京後に、この床屋は更に丁寧な礼状をよこしました。父は、これを手にして「日本の総理大臣から感謝状を受け取りましたよりも有難いです」と申しました』(小泉一雄手記)
この床屋は、焼津市焼津柳町九百番地の進陽軒といって、八雲が東京から毎年夏に、山口乙吉の家の二階を借りて避暑にでかけたときに、いつも髭を当たらせていた。ナイフを研がせた頃の主人は進藤広吉さんというひとだった。
明治三十三年の話で、八雲がアメリカの友人に書き送った手紙。
「東京には神様はいないが、焼津には神様がいる」と、いった――神様の村。焼津の理容店のエピソードである。
参考:「全訳小泉八雲作品集」(小泉一雄)、「文学散歩」「文学散歩通信」(野田宇太郎)
